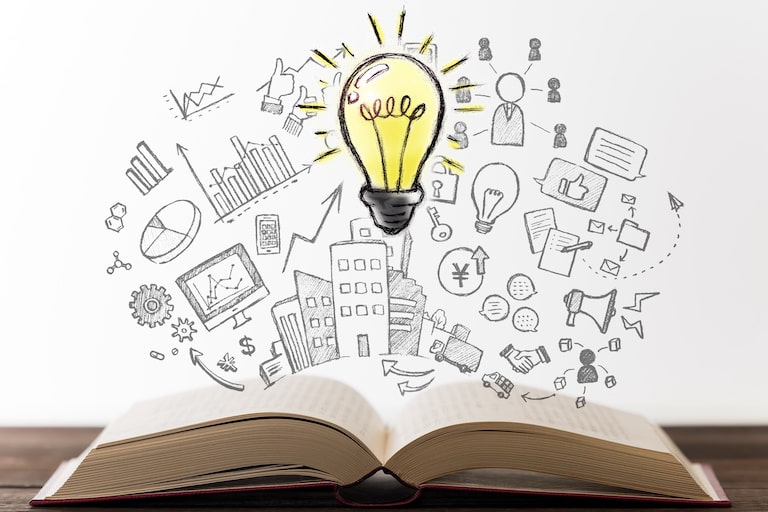「改正電子帳簿保存法対応を英語圏スタッフに説明するには?」
「英語圏スタッフに電子帳簿保存法を説明する際のポイントを知りたい」
と疑問に感じていませんか。
改正電子帳簿保存法対応は一般スタッフの協力なくしては実現ができません。もちろん自社内に英語圏など外国人スタッフがいれば、彼らの協力も不可欠です。
したがって、外国人スタッフに対して電子帳簿保存法対応を説明する必要があります。
当記事では、改正電子帳簿保存法の概要、英語圏スタッフ等に電子帳簿保存法対応を説明する際のポイントについて解説します。
2022年1月に電子帳簿保存法が改正された

電子帳簿保存法とは国税関係帳簿や国税関係書類を電子的に保存してもよいと認めた法律です。
電子帳簿保存法の現行概要
電子帳簿保存法は国税庁により1998年に施行されてから、2022年1月にいたるまで改正を繰り返してきています。常に世の中のペーパーレス化を後押しする形式で電子帳簿の保存要件を変化させてきているのです。
2022年1月の改正では電子帳簿保存法全体で要件が緩和されました。一方で、改正により電子取引した文書は必ず電子保存する要件が盛り込まれたため、多くの企業が電子帳簿保存法対応準備に追われています。
電子帳簿保存法は保存する電子文書の種類によって、以下の4つの保存要件区分があります。
- 国税関係帳簿データ(帳簿保存の要件区分)
- 決算関係書類など国税関係書類データ(書類保存の要件区分)
- 紙の電子化データ(スキャナ保存の要件区分)
- 電子的に相手方とやりとりした文書データ(電子取引保存の要件区分)
電子取引要件対応を2023年12月までに実施する必要がある
上記4つの要件区分の内、電子取引対応については2023年12月までに対応をする必要があります。
本来であれば、2022年1月に電子帳簿保存法改正法が施行された段階から対応が必要でしたが、2022年1月の時点で電子帳簿保存法に対応できる企業が少なかったことから、国税庁により対応期日が延長されているのです。
2年間の延長(宥恕措置)が実施されたため、2023年12月までに対応が必要になります。
もし、2024年1月以降の国税調査時に電子帳簿保存法の要件を満たさずに保存をしている旨を指摘された場合、ペナルティが課される場合もあると国税庁より公表されていますので、確実な対応をしましょう。
2024年1月以降にも猶予措置はあるが適用が難しそう
2022年12月に2024年1月以降の電子帳簿保存法に対する改正予定、税制改正大綱が国税庁により公表されました。税制改正大綱によれば、2024年1月以降は以下の要件を満たすことで、電子取引した文書の書面保存が認められています。
- 保存要件に従って保存ができなかった相当の理由があること
- 電磁的記録のダウンロードの求めに応じること
- 電磁的記録の出力書面の提示または提出ができること
ただし、上記の要件を満たして対応をする場合、書面と電子の二重対応が必要になる点に注意が必要です。なぜなら、電磁的記録のダウンロードの求めに応じ、かつ、書面の提示をするからです。
したがって、上記の猶予措置の適用を受けようと考えると、工数がかかることが想定されるため、多くの企業では2023年12月までの電子帳簿保存法 電子取引要件対応完了を目指しています。
企業の一般スタッフにも関連するため英語圏スタッフ等への説明も必要
電子帳簿保存法 電子取引要件対応をする場合、企業に所属する一般スタッフの協力が必須です。なぜなら、相手方と電子的にやり取りした取引情報は全て保存対象であるからです。
したがって、もし企業内に英語圏のスタッフなど、日本の法律についてあまり詳しくない社員がいたとしても、ある程度は理解してもらって協力してもらう必要があります。
とはいえ、日本人でも理解が難しい法律を英語等で伝えるのは難易度が高いですので、英語圏のスタッフなどの外国人スタッフには伝えるべき内容を抑えて伝えるようにしましょう。
英語圏スタッフ等に説明する際のポイント

電子帳簿保存法 電子取引要件について、英語圏スタッフなど外交人スタッフに端的に伝えるポイントは以下の通りです。
- 英語圏スタッフ等への説明ポイント①:電子取引したら必ず保存が必要であること
- 英語圏スタッフ等への説明ポイント②:遅くても2か月+7営業日以内に保存が必要であること
- 英語圏スタッフ等への説明ポイント③:情報の保存時には検索値を記録・付与すること
- 英語圏スタッフ等への説明ポイント④:編集削除をするときには申請すること
英語圏スタッフ等への説明ポイント①:電子取引したら必ず保存が必要であること
電子帳簿保存法 電子取引要件をする必要がある文書は電子取引をした取引文書です。したがって、例えば担当者レベルで以下のような取引をした場合には記録・保存をしてもらう必要があると認識してもらう必要があるのです。
- メールに添付された請求書など
- EDI経由で授受した納品情報など
- 電子契約サービス経由で受領した契約書など
英語圏スタッフに対して、上記のような取引をした場合に記録・保存が必要になる旨を説明しておくようにしてください。
英語圏スタッフ等への説明ポイント②:遅くても2か月+7営業日以内に記録・保存が必要であること
電子帳簿保存法 電子取引要件では、授受した取引情報を授受した日から遅くても2か月+7営業日以内に記録・保存する必要があります。
保存とはファイルサーバー上にただ記録・保存すればよいわけではなく、真実性、可視性を確保した状態での記録・保存が必要です。
わかりやすい例で言えば、2か月+7営業日以内にタイムスタンプを付与できるようにしてくださいという案内になるかと思います。
このように電子取引した取引情報をただ記録・保存するだけでなく、電子帳簿保存法 電子取引要件で求められる要件を満たした状況に2か月+7営業日以内にする必要があると英語圏スタッフなどに説明しておくようにしましょう。
英語圏スタッフ等への説明ポイント③:情報の保存時には検索値を記録・付与すること
電子帳簿保存法 電子取引要件では電子的にやり取りしたファイルを主要3項目で検索できる必要があります。
OCRなどを利用することで、やり取りしたファイルをシステムに取り込みさえすれば、検索に必要な名称月のデータ作成・検索が可能な状況にできるのであれば問題ありません。
ただし、現実的にはOCRの読み取り制度などの問題があり検索値を手動で記録・付与する場合も多いようです。
もし、英語圏スタッフを含む現場スタッフにファイルへの検索値付与を手動でお願いする場合には、どのような値をファイル上のどこに入力する必要があるのか事前に説明が必要になるでしょう。
英語圏スタッフ等への説明ポイント④:編集削除をするときには申請すること
電子帳簿保存法 電子取引要件対応をする場合、多くの場合で訂正削除の防止に関わる事務処理規程を作成することになるかと思います。
事務処理規程上には、システム上に保存した文書の訂正削除に関する業務運用について、記載することになります。その中で文書の削除訂正をする場合には、管理者に届け出を提出して、中央で記録する運用にする方が多数です。
したがって、英語圏スタッフ含む現場担当者に対して、一度格納した文書を修正する際には管理者に届け出を出して承認をもらう旨を周知する必要があるでしょう。
まとめ 英語圏スタッフ等が理解しやすい運用を整備しよう
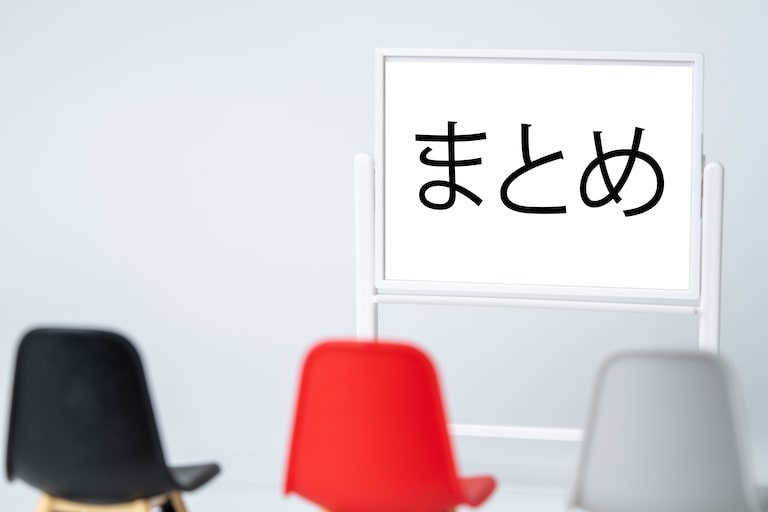
電子帳簿保存法対応を進めるためには英語圏スタッフを含む現場スタッフの協力が不可欠です。一方で、電子帳簿保存法を英語訳しているドキュメントは少ないですので、説明にかける工数が高くなりがちな点が課題といえます。
したがって、電子帳簿保存法についての説明量をそもそも少なくするためにも、シンプルな業務運用を設計して、スタッフへの説明をしやすくするなどの工夫が必要です。
最も簡単に電子帳簿保存法対応をシンプルにする方法は法対応したシステムを導入することです。ぜひシステムを導入する際には業務運用にも気にして検討ください。